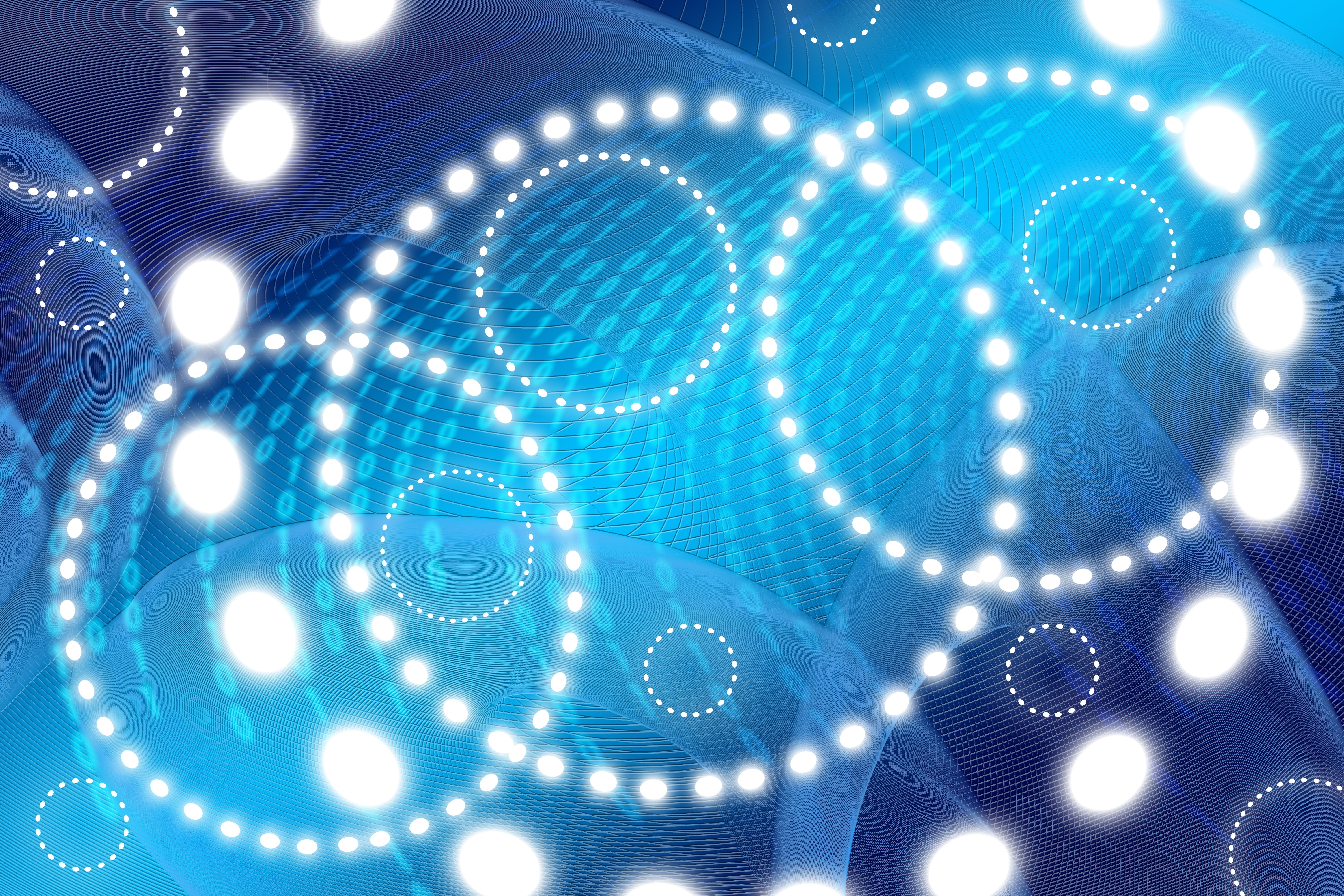◆第169回新語・語法研究分科会のご案内(2026/02/14開催)
新語・語法研究分科会では下記の通り、第169回新語・語法研究分科会を開催いたします。今回は、秀明大学の山西敏博氏に、「国歌:外国と日本の歌詞の相違」をテーマに発表していただきます。
cf.)第136回(2017年11月11日)新語・語法研究分科会(https://james.or.jp/author/secretariat/page/24)
日時:2026年2月14日(土)14:10–16:00
場所:ZOOM(IDおよびパスワードは出席予定者に直前に通知いたします)
1.新語フォーラム(14:10-15:00) 司会:山内 圭(新見公立大学)
発表をご希望の方は、2月7日までにレジュメを三田までお送りください。
お一人様の発表時間は最大10分、新語は1語から3語までの範囲でご紹介いただければ幸いです。
2.研究発表(15:05–15:45) 司会:三田 弘美(口語英語研究所)
題目:国歌:外国と日本の歌詞の相違
発表者:山西 敏博会員(秀明大学)https://www.shumei-u.ac.jp/staff/34623
内容:本発表は、外国と日本の「国歌」に焦点を当て、その歌詞の意味合いの違いに対して着目をすることを目的とします。アニメ「ドラえもん」の「ジャイアン」ばりに、他人の所有物も自分の物として奪い取ろうとする党首が席巻される、昨今の世界情勢。その根底は「国歌」に根付く無意識下の意識にあるのではないかとさえ考えてしまいます。他方、戦後81年間、一切の対外戦争を起こしてはいない日本国。この違いはどこから起こるのか、「国歌の歌詞」に焦点を当てて推察します。真の世界平和を希求しつつ・・
参加をご希望される方は、三田< hiromitissot [a]yahoo.co.jp >までご連絡ください。 (アットマークに変換してください)
新語にご関心のある方、今回の研究発表の題目にご興味をお持ちの方、また初めての方も、どうぞお気軽にご参加くださいませ。
皆様からのご連絡をお待ちしております。
新語・語法研究分科会 代表 三田 弘美