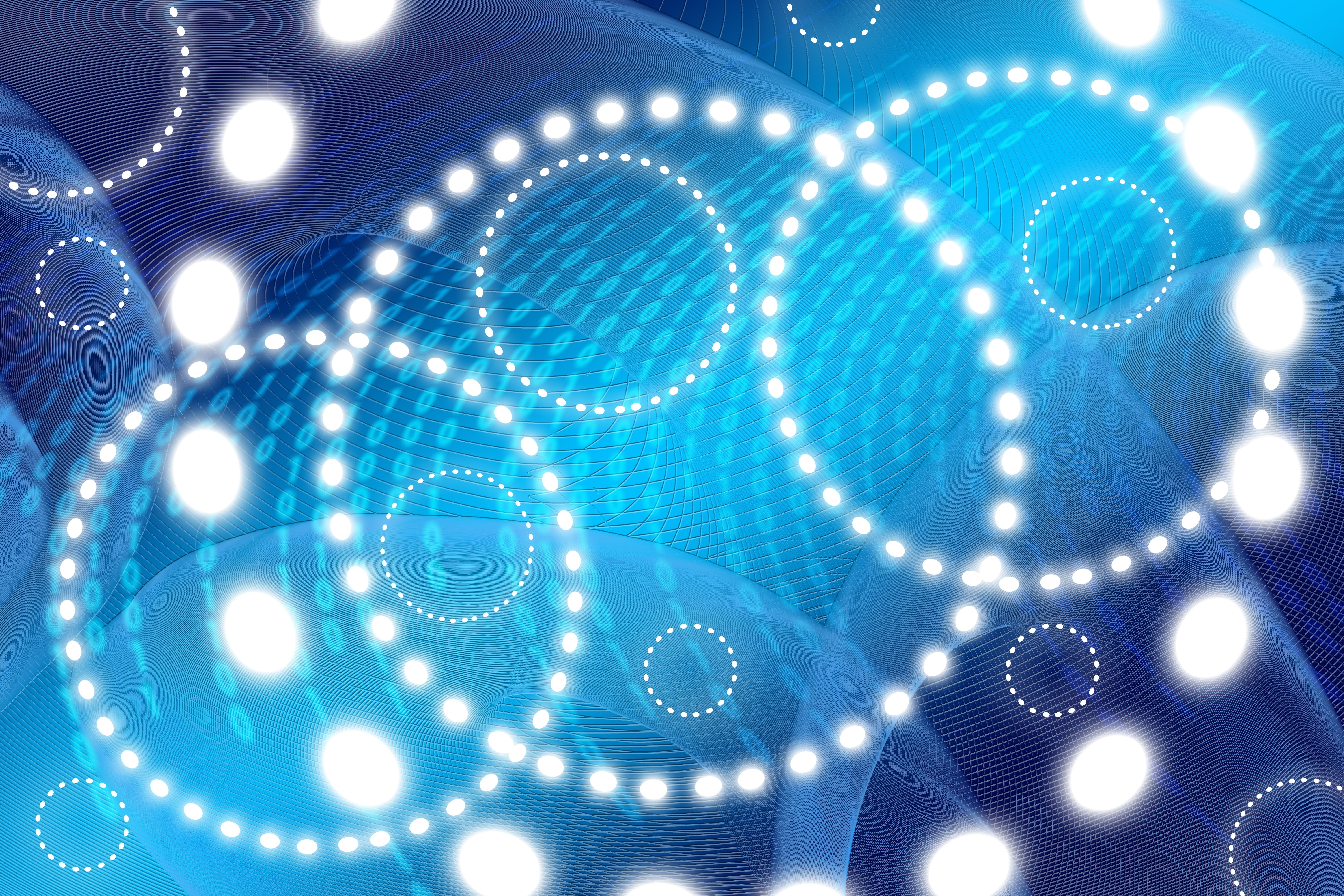中部地区第66回研究例会(12月20日@愛知大学)
中部地区第66回研究例会を以下の要領で行います。
多数の方のご参加をお待ちしています。
【日時】 2015年12月20日(日) 14:00-16:30
【会場】 愛知大学名古屋キャンパス 8階 L801教室
*名古屋駅より名駅通を南下(徒歩10分程度)、またはあおなみ線ささしまライブ駅より徒歩すぐ
【参加費】 会員・非会員ともに無料
【発表】
第1部 研究発表(14:00-15:00)
久保田絢会員(愛知淑徳大学)
「英語プレゼンテーションの指導法に関する一考察」
第2部 招待講演(15:15-16:15)
川村亜樹先生(愛知大学)・佐藤良子先生(愛知大学)
「グローバル人材育成支援事業を通した『語学力』『日本理解・発信力』の養成」
【発表要旨】
「英語プレゼンテーションの指導法に関する一考察」
久保田絢会員(愛知淑徳大学)
英語に対する苦手意識のある学生が萎縮せず主体的に学習に取り組む学習環境をいかにデザインするかという課題について、愛知淑徳大学ビジネス学部における英語プレゼンテーションの授業実践を例に考察する。
「グローバル人材育成支援事業を通した『語学力』『日本理解・発信力』の養成」
川村亜樹先生(愛知大学)・佐藤良子先生(愛知大学)
2012年からA大学は、現代中国学部を中心として、文部科学省の「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援(特色型)」に採択され、グローバル人材育成に取り組んでいる。そこで本発表では、本事業における「語学力」「日本理解・発信力」の養成について報告する。「語学力」では、主に香港浸会大学でのビジネス英語研修の事例紹介をおこなう。「日本理解・発信力」では、メディアの活用に焦点を当てて、「さくら21プロジェクト」での取り組みについて事例を報告する。これらを踏まえ、グローバル企業の即戦力を目指す人材育成のための、今後の具体的な英語研修、日本理解・発信の在り方について検討したい。
*なお、例会終了後、講師を招いての懇親会(名古屋駅前、会費5000円程度)を企画しております。
予約の都合上、参加をご希望の方は、事前に石原(下記連絡先)までご連絡をいただけますと助かります。
【問い合わせ先】 石原知英(愛知大学)(Email: tishiha[a]vega.aichi-u.ac.jp)([a]を@に変えてください)