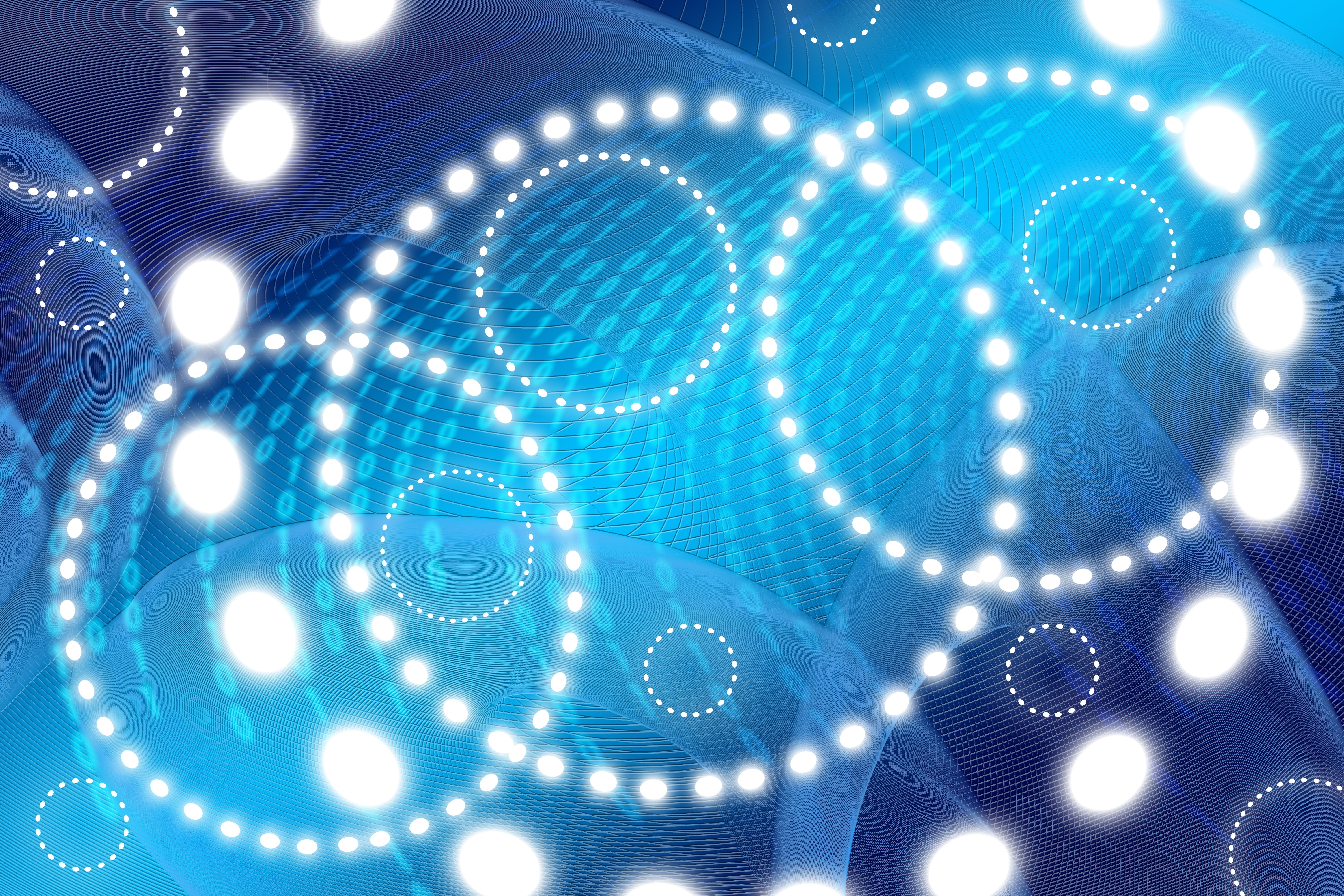第122回西日本地区研究例会のお知らせ
下記要領にて、西日本地区研究例会を開催いたします。多数のご参加をお待ちいたしております。
日時: 2016年7月30日(土) 午後2時~午後5時(午後1:30受付開始)
場所: 大阪府立大学I-siteなんば 2階S1教室 (※中百舌鳥キャンパスではございません)
http://www.osakafu-u.ac.jp/isitenanba/map/index.html
大阪市浪速区敷津東2丁目1番41号 南海なんば第1ビル2階 Tel 06-7656-0441(代表)
会費: 無料
発表者① 宮崎 康支(新入会員)
「発達障害の概念と、新聞記事における言語表現」
近年、教育や福祉などの領域において、自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などといった、発達障害をもつ人々への対応が話題に上ることが多くなった。しかし、発達障害をめぐるイメージがどのように形成されているか、またそのイメージの形成において言語がいかに作用しているか、といった点が議論されることは少ない。本発表においては、日本の新聞記事における発達障害の概念の語られ方と、言語表現の関連性についていくつかの事例を挙げて議論する。また、英語圏における発達障害の用語がどのように日本において翻訳されているか、という論点についても言及する。
発表者② 仲川 浩世(会員)
「メディア英語を利用した発信型能力育成の可能性」
本研究の目的は、メディア英語を利用した学習者の発信型能力の育成である。メディア英語(時事問題)に対して、自分の意見を英語で話し、書かせるという指導を行った。対象は、外国語学部英検準1級対策クラスの大学生である。過去の英検に出題された時事問題に対して、自分の意見を英語のパラグラフで2度書かせた。また毎週担当者を決め、類似のテーマに対して、英語のスピーチをさせた。この結果、教材のインプット⇒授業内でのアウトプット⇒学習者同士のインプット⇒ライティングのアウトプットという過程を経て、コンテンツや語彙の強化が見られるようになった。本発表では、学習者のパラグラフやフィードバックについても紹介する。
発表者③ 渡部 敬子(会員)
「「国連に於けるパレスチナオブザーバー国家承認」報道記事のディスコース分析——前提要件の分析によるアプローチ」
本研究は、「国連に於けるパレスチナオブザーバー国家承認」報道記事を取り上げ、コンテクストにどのような前提要件が働いているかに着目してディスコース分析を行う。「パレスチナ問題」は、実際には欧米の植民地主義によるものであり(ラブキン、2012)、そのことに対するパレスチナ人の抵抗(板垣2015)であるにもかかわらず、イスラエルとパレスチナ人との「対立」や「闘争」であるかのように認識されていると思われる。分析を通してパレスチナ問題報道のコンテクストにある前提がどのように「対立関係」を作り上げているかを検証する。
~発表者紹介~
宮崎 康支(みやざき・やすし)
関西学院大学大学院総合政策研究科博士課程後期課程在籍。香川県出身。関西国際大学人間学部英語コミュニケーション学科を卒業後、関西学院大学大学院に進学。修士号取得後に福祉系の仕事を経験し、米国Syracuse Universityにて障害学を学ぶ。帰国後2014年に関西学院大学大学院総合政策研究科博士課程後期課程に進学し現在に至る。社会言語学や談話分析、さらに言語政策論などの枠組みを用いて、障害や在住外国人などに関する問題を分析している。
仲川 浩世(なかがわ・ひろよ)
関西外国語大学短期大学部 准教授。カナダのオタワにあるCarleton Universityにて応用言語学の修士課程を修了。TOEIC関連の対策書などテキストを多数出版。最近の主な研究テーマはライティング指導、自律的な学習者育成などである。
渡部 敬子 (わたべ・けいこ)
1982年成蹊大学文学部英米文学科卒業(イギリス近代文学専攻)。高校で教鞭を執る中、英語を勉強することのさらなる必要性を知り、ディスコース分析という言語学分野を学ぶために、2000年成蹊大学英米文学研究科博士前期課程に入学。指導教授の浅野雅巳先生のゼミでメディア言語の分析において批判的ディスコース分析という視点があることを知る。修士論文では、1948年イスラエル国家建設についてのアメリカの新聞報道記事を取り上げ、invade という語を巡ってディスコース分析を行った。2002年4月に同大学博士後期課程に進学。研究の目的は、「パレスチナ問題」報道の根底に在るイデオロギーを言語分析によって明らかにすることである。2005年3月、同大学院を満期退学。2002年より本学会のメディア英語談話分析研究分科会のメンバーとしてCDAの研究を続けている。現在、山梨県立北杜高等学校非常勤講師。
問合せ先:日本メディア英語学会 西日本地区長 仲西恭子 kyoko-i@kansaigaidai.ac.jp