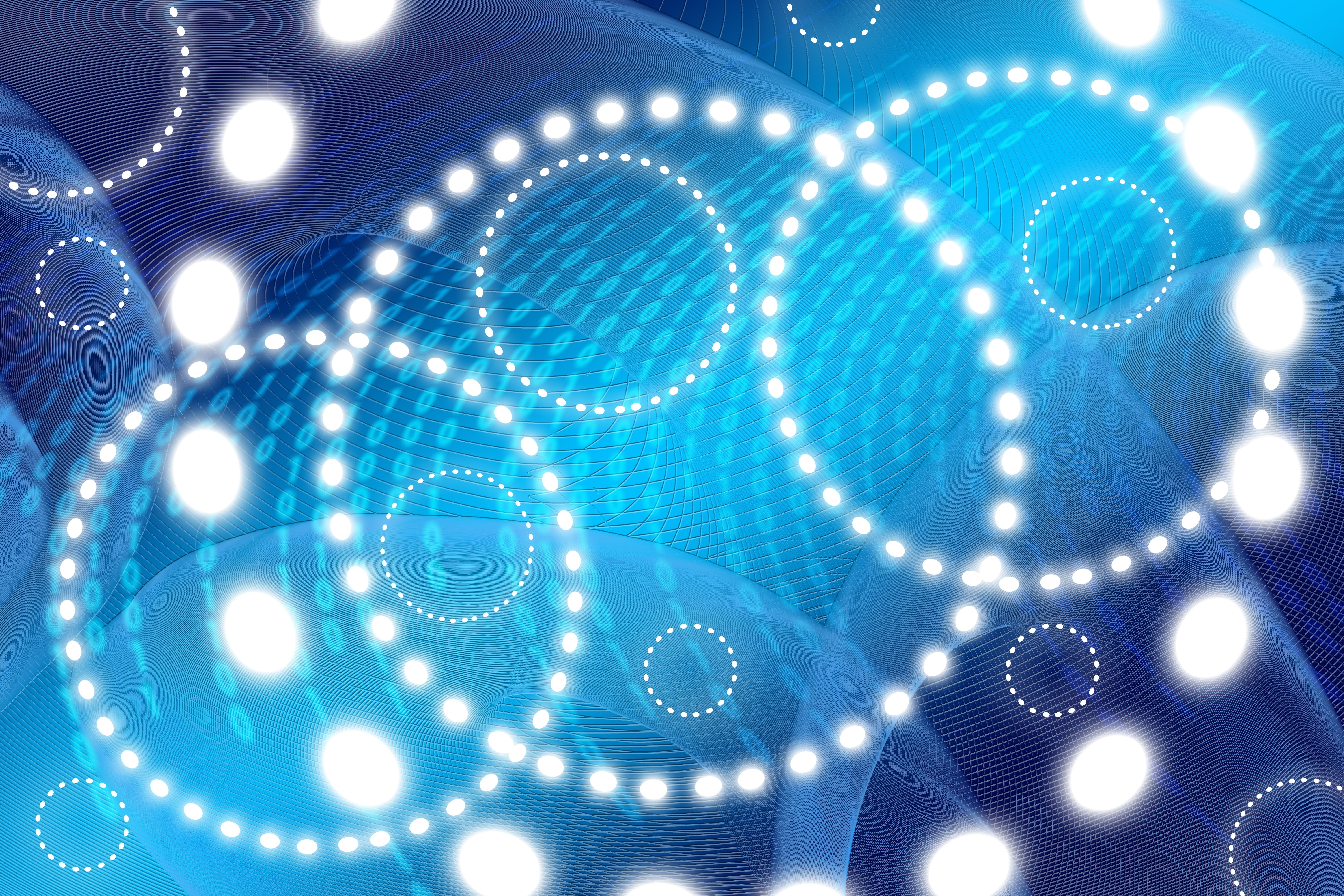第126回西日本地区研究例会のご案内
下記の通り、第126回西日本地区研究例会を開催いたします。今回は、教育における通訳翻訳の可能性についてのシンポジウムを開催いたします。どうぞ奮ってご参加いただけますよう、ご案内申し上げます。
日時:2018年9月15日(土)
14:00~17:00(13:30受付開始)
場所:佛教大学二条キャンパスN1-211
http://www.bukkyo-u.ac.jp/about/access/nijo/
〒604-8418 京都市中京区西ノ京東栂尾町7
JR嵯峨野線二条駅・京都市営地下鉄(東西線)二条駅から徒歩1分
参加費:無料(予約不要)
シンポジウム
教育と翻通訳~どのメディアをいかに教育に応用するか~
概要:本シンポジウムでは、通訳翻訳の実務家もしくは通訳翻訳研究の専門家ではない諸氏が、教育における英日語の通訳翻訳について、通訳学のみならず、ジャーナリズム研究、文学研究、第二言語習得研究の立場から報告する。どの素材を用いて翻訳通訳を授業で行なっているのか、そして、教育における通訳翻訳の位置付けやその目的、効果など、教育における通訳翻訳の様々な側面について問題を提起する。各パネラーの報告を受け、教育における通訳翻訳の裾野を広げ、教育における通訳翻訳の定義の多様性について議論を重ね、理解を深める。
スケジュール
14:00~14:05 開会挨拶
14:05~14:10 パネラーの紹介と言語教育における通訳翻訳の動向
南津佳広会員(大阪電気通信大学)
14:10~14:35 「『ニュース翻訳塾』でメディア業界就職を後方支援」
金井啓子会員(近畿大学)
14:35~15:00 「思考の軌跡をたどる―文学テクストの翻訳の可能性―」
杉村寛子会員(大阪電気通信大学)
(10分休憩)
15:10~15:35 「理系学生X翻訳 読みを深めるための取り組み」
工藤多恵会員(関西学院大学)
15:35~16:00 「逐次通訳訓練手法はモノローグ・スピーチ産出の訓練にどこまで貢献しうるか」
南津佳広会員(大阪電気通信大学)
(15分休憩)
16:15~16:55 各発表者のまとめとフロアからの質疑応答
16:55~17:00 閉会挨拶
■金井啓子会員(近畿大学)
【題目】「『ニュース翻訳塾』でメディア業界就職を後方支援」
【概要】メディア業界を目指す学生を主な対象とする有志の勉強会『ニュース翻訳塾』について検討する。勉強会では、学生が既に日本語では内容に触れている社会的事象に関して英語メディアが報道した記事を翻訳させて話し合い、英語の読解力を高めると同時に、独自の切り口への理解を深めることを目指している。翻訳の評価手法、勉強会に関するメリットやデメリット、勉強会における翻訳の定義などに触れていく。
■杉村寛子会員(大阪電気通信大学)
【題目】「思考の軌跡をたどる〜文学テクストの翻訳の可能性〜」
【概要】所与の世界を言語化する文学テクスト。読者はことばを拠りどころとし、自らが生きる文脈に基づき、同時にテクストが産み出された文脈も意識しつつ、そのテクストの世界をイメージし、構築していく。この解釈の過程はまさにひとつの思考であり、教室において文学テクストを読ませる者にとって興味は尽きない。そこで、翻訳という読者による言語化によって、その思考の軌跡をたどれるのではないかと考えた。本発題では、多様な解釈に開かれた文学テクストの翻訳が思考の深化に如何に関係するか探りたい。
■工藤多恵会員(関西学院大学)
【題目】「理系学生X翻訳 読みを深めるための取り組み」
【概要】最先端の論文を読むため、理工系の学生にとって英語は重要なツールである。英語の授業でも科学系のリーディン教材をskimmingやscanningなどのスキルを使って速読する演習が重視されがちである。このような通常の授業内容とは別に、実験的に「翻訳」をタスクとして導入したところ、その課題の結果から、翻訳には正確に英文を理解する力だけでなく、コンテクストを意識した深い読みが必要とされることが示唆された。本発表では、翻訳がもたらす教育効果について考察する。
■南津佳広会員(大阪電気通信大学)
【題目】「逐次通訳訓練手法はモノローグ・スピーチの訓練にどこまで貢献しうるか」
【概要】本研究では、学部レベルにおける英語教育でのスピーキング指導にて、逐次通訳訓練で行われるノート・テーキング(通訳メモ)の訓練手法を応用して導入した結果を報告する。この通訳メモの訓練手法を応用し、学習者が 即応的に英語を産出する訓練を行った。通訳メモを導入する狙いは、学習者の言語産出プランを可視化させる ことができ、それを手がかりに、文法的に的確で論理的なモノローグを英語で制限時間内に即応的に構成させることにある。通年(90 分×30 回)で行った結果を分析し、学習者が発話に躓く際の発話メモのエラーの特徴やその介入などにも触れる。
問い合わせ先:
稲永知世(西日本地区長)
(inenaga@bukkyo-u.ac.jp)